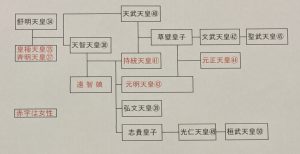甲冑 兜 ~その十六~
鏡獅子からスピンアウト 「鏡とヘビ」
ちょっと宣伝
当店は五月五日まで営業しています。すでに端午の節句の販売を終えてしまったお店もあるようですが、当店は五日まで営業しています。
それは、五月四日にお誕生のお子様にとっても五日は初節句となるからです。毎年のように、五日近くなってお誕生のお子様の初節句用にお客様がいらっしゃいます。玩具やインテリアならいざしらず、お節句の品を扱う以上、五日まで店を開くのは節句品店の務めです。どうぞ、三日、四日にお誕生のお子様にも初節句のお祝いをしてあげて下さい。

こんな本格的作りで可愛らしい節句飾りもございます
5万円程(幅60cm)
手作りの木目込人形(兜に菖蒲)。
手作り木綿ののぼり旗、鯉のぼり。
雲母摺り京唐紙の屏風。
純木製(セン、エンジュ)の台(ベニヤ・MDF不使用)
拙著「いま、伝えたい節句のお話」で鏡獅子と鏡餅のことにふれました。鏡餅開きのときに獅子の精が乗り移って舞うことから「鏡獅子」と名付けられているのですが、鏡餅はなぜ「鏡」なのでしょうか。どちらも同じように円くて大切なもの、という関連だけでは鏡餅を二段、ときには三段に積み重ねる理由がわかりません。
ヤマカガシというヘビがいます。北海道などを除きどこにでもいるヘビですが、この、カガシというのが古来からのヘビの和名といわれています。平安時代の和名抄にはヤマカガシのことを「夜萬加々智」と載せています。
民俗学の吉野裕子はカガがヘビの古名であるとしてさまざまな検証をしていて、その中に鏡(カガミ)とヘビとの関係性を指摘しています。鏡餅のあのかたちはヘビのトグロからきているのではないかというのです。私はヘビがあまり好きにはなれないので全面的に賛成はしかねますけれど、たしかにうなづける面はあります。少なくとも「鏡→鏡餅」よりは「ヘビのトグロ→鏡餅」の方が、形状の面では似ています。
鏡が日本に伝わったのは弥生時代といわれていますが、ヘビの古名「カガ」がいつごろからあるのかわかりません。もし、カガの言葉が先にあって鏡の名にこの言葉を適用したのならば、それはなぜなのか。また、カガが後とすれば、なぜ鏡の呼び名にヘビを用いるようになったのか、はたまた、カガミのカガはヘビとはもともと関係なくたまたまそのような名前になっただけなのか、興味は尽きません。
ずいぶん甲冑から脱線しましたが、次回から甲冑のお話に戻そうと思います。
節句文化研究会では、こうした 面倒臭いけどなんだか楽しい節句のお話を出前しています。カルチャースクール、各種団体、学校などお気軽にお問合せください。→HP最後のお問い合わせメールからどうぞ
これまで、いくつかの和文化カルチャースクール様、ロータリークラブ様、徳川美術館様、業界団体様、中学の授業などでお話させていただいています。
※この記事の無断引用は固くお断りします。